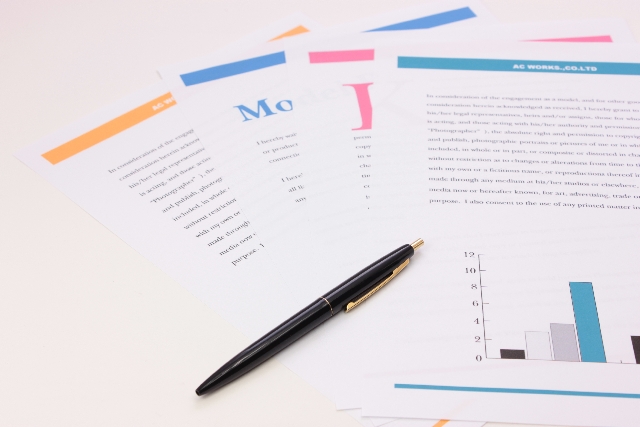


遺産相続について無知すぎるのですが
回答お願いします。
父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。
父の弟は、結婚し子供が3人います。
祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。
お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。
父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。
遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?
株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。
うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。
弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
回答お願いします。
父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま
父方の祖母もなくなりました。
父は、長男で弟がいます。
父は、母との間に息子1人娘
1人(わたし)で離婚し再婚しましたが
また、離婚してます。再婚のさいに子供はいません。
父の弟は、結婚し子供が3人います。
祖父がなくなり祖母と私の二人ですんでいましたが祖母も亡くなり名義も変えぬまま世帯主だけが私になり
祖母の家にすんでいました。
亡くなってからの固定資産税は私がはらっていました。
お盆に家族であつまり
長年放棄されていた遺産相続をすることになりました。
父は、相続について無知なので
変わりに私が質問しているのですが。
遺産相続は、長男と次男で2分の1で
間違えないですか?
株、土地、預金どのくらあるのかも
分からないそうです。
弟は、お金の話になると
決まって逃げ帰っていました。
父がゆうには保険金などは、
もぅ、使っているのでは?
とのことです。
うまく言いくるめられないために
対策をしたいのですが
父は今定年退職後失業保険での生活です。
弁護士を立てる費用は難しい状態にあります。
どうしたら良いのか全くもってわかりません。
教えて頂けないでしょうか
「父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま父方の祖母もなくなりました」と書いているのは、相続というものの性格を理解していない間違った表現です。
祖父が死亡した瞬間に相続は発生しています。法定相続人が複数いる場合には、祖父の遺産を共有した状態で相続しているのです。通常は、その後、相続人同士の話し合いで誰が何を相続するのか、という遺産分割について取り決めをする段取りをふみます。
当然、父親も、祖父や祖母の死亡の瞬間に相続をしているのであり、「父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま」だったのではなく、「父方の祖父がなくなり遺産分割について取り決めをしないまま」祖母も亡くなったのです。
相続の割合については、祖父の相続については、妻である祖母が半分を相続し、残り半分を子供であるあなたの父及びその弟であるあなたにとっては叔父に当たる人が均等割して相続します。
祖母の相続については、配偶者が生存していないため、子供二人が均等割して相続するのが法定相続の規定です。
しかし相続人の一人であるあなたの叔父が分割協議に協力的でないのに、法律の素人である父やあなたの力のみ、付け焼き刃の知識のみで分割協議がどうして進められると考えるのですか。
そういう発想をどうしてなさるのか、不思議でなりません。
祖父が死亡した瞬間に相続は発生しています。法定相続人が複数いる場合には、祖父の遺産を共有した状態で相続しているのです。通常は、その後、相続人同士の話し合いで誰が何を相続するのか、という遺産分割について取り決めをする段取りをふみます。
当然、父親も、祖父や祖母の死亡の瞬間に相続をしているのであり、「父方の祖父がなくなり遺産相続しないまま」だったのではなく、「父方の祖父がなくなり遺産分割について取り決めをしないまま」祖母も亡くなったのです。
相続の割合については、祖父の相続については、妻である祖母が半分を相続し、残り半分を子供であるあなたの父及びその弟であるあなたにとっては叔父に当たる人が均等割して相続します。
祖母の相続については、配偶者が生存していないため、子供二人が均等割して相続するのが法定相続の規定です。
しかし相続人の一人であるあなたの叔父が分割協議に協力的でないのに、法律の素人である父やあなたの力のみ、付け焼き刃の知識のみで分割協議がどうして進められると考えるのですか。
そういう発想をどうしてなさるのか、不思議でなりません。
11月もしくは12月末に会社都合で派遣の仕事を終了予定のものです(部署閉鎖の為)。退職後は会社都合の為すぐに失業保険を受給し、その後はすぐく夫の扶養に入りたいと考えているのですが可能でしょうか?
雇用保険受給期間中は扶養には入れません(受給額が少なければ(手当日額3,611円以下)扶養も可能)
※受給後であれば入れるでしょう。
※受給後であれば入れるでしょう。
失業保険の受給金額について質問です。
失業保険の受給金額について質問です。
22歳で入社し51歳でその会社を退職し、別会社に再度就職し(前会社の系列)定年退職を迎えた
場合に失業保険は1日あたりいくらもらえるのか、そして受給期間とその総額はいくらになるのでしょうか?
失業保険の延長の可能性を含めて宜しくお願いします。
失業保険の受給金額について質問です。
22歳で入社し51歳でその会社を退職し、別会社に再度就職し(前会社の系列)定年退職を迎えた
場合に失業保険は1日あたりいくらもらえるのか、そして受給期間とその総額はいくらになるのでしょうか?
失業保険の延長の可能性を含めて宜しくお願いします。
詳しい事はハローワークのホームページへどうぞ。
社会常識として保険と言うのは支払ったものに見合うものですが、直近の数ヶ月の給料から算出されます。
長い期間加入していればそれに見合った期間の支給になります。
60歳以上と未満では給付月数が異なります。
年金との併給は不可です。
それに、給料明細にも記載されていたはずで雇用保険です。
社会常識として保険と言うのは支払ったものに見合うものですが、直近の数ヶ月の給料から算出されます。
長い期間加入していればそれに見合った期間の支給になります。
60歳以上と未満では給付月数が異なります。
年金との併給は不可です。
それに、給料明細にも記載されていたはずで雇用保険です。
失業保険について
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
2年務めたS社をやめて、現在R社に務め1ヶ月がたちました。
正直やめようと思っています。会社説明時と何もかもが違ったので、、、
本題はやめたあとに、ハローワークでS社の離職票を使って、失業保険の給付ができるのか?ということです。
回答お待ちしてます。
雇用保険の失業手当(=基本手当)を受給するには、いくつかの条件があり会社を退職したからといって、必ず失業手当をもらえるとは限りません。受給するには、次の条件を全て満たしている必要があります。
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)
転職した場合は、それぞれの会社での被保険者期間を、合計することができます。ただし、前の会社の退職後に失業手当をもらっていたり、再就職までの期間が1年を超えているときは、通算できません。
また、病気やケガなどで30日以上会社を休み、その期間の給料がもらえなかったときは、その期間は延長されます。
例えば、60日間病欠で会社を休み、その期間に給料をもらえなかったときは、
1年+60日の間で、6カ月以上の被保険者期間があればよいのです。(ただし、最長3年間までの制限があります。)
その他、1週間の労働時間が20時間以上30時間未満の、パートやアルバイトの人のケースがあります。
これらの人は、離職直前の2年間で1カ月あたり11日以上働いた月が、通算して12カ月以上あればOK。 *詳細 →パート、アルバイトの雇用保険
派遣社員については、派遣社員の雇用保険をご覧ください。
なお、雇用保険の失業手当が受給できないケースは、次のようになっています。
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき
例外として、以下のケースでは失業手当の受給期間の延長の手続きをすれば、失業手当を受け取れます。
・妊娠、出産、育児、ケガ、病気などですぐに働けないとき
・病人の看病ですぐに働けないとき
・定年退職後に一時的に休養するとき
関連する情報